9日(月曜)のワシントンポストに「Patient Web sites used for news, support in crisis」という記事が掲載された。ここで紹介されているのはCareBridgeとCarePagesで、当方ブログの以前のエントリで紹介済み(こことここ)だが、両者とも患者簡易サイトのホスティングサービスとして古参と言ってもよいだろう。CarePagesのほうは、スティーブ・ケース氏率いるRevolutionHealthに買収されたようだ。
このワシントンポストの記事を一読して思ったのは、なぜ今頃、CareBridgeやCarePagesを取り上げるのだろうかという素朴な疑問である。TOBYOで闘病記にフォーカスしている当方の目から見ると、CareBridgeもCarePageも、どちらも闘病サイトのホスティングサービスを提供しているわけだ。たしかにブログが登場する以前には、両者とも「簡易ホームページ」を提供してくれるサービスとして、それなりの利用価値はあっただろう。だがブログ登場以降、これらのサービスは明らかに陳腐化しているはずなのだが、それが、いまだにワシントンポストの「ニュース」になっていること自体、不思議に思える。
しかし、CareBridgeやCarePagesに該当するサービスは日本にはまだない。日本の医療関連ウェブサービスを過去十年ほど概観すれば、医療機関側、医療者側の情報を消費者、闘病者側に伝えるものがほとんどすべてであった。それは、今だに林立する「病院検索サービス」の類を見ればわかるだろう。「医療界→消費者・闘病者」という単方向でしか、日本の医療関連ウェブサービスは事業を構想できなかったのであり、患者発の情報を無視するか、あるいは決定的に見落としていた。これは医療界、アカデミズム、役所、マスコミ、企業、NPO他各種団体など、すべてに言えることであり、一部団体では「インターネットで医療を変える」など言辞を弄しつつも、結局はネットと闘病者のパワーを過小評価してきたと言うほかない。だが、ネットユーザーや闘病者は、以上のどの関係者よりも先を進んでいたのである
ここ10年ちょっとの間に、日本では闘病者が自分の体験を自発的に次々にネット上に公開し、「闘病ネットワーク圏」と呼ぶべき情報共有空間が自生的に形成されてきた。つまり、米国でCareBridgeやCarePagesが提供していた情報共有サービスを、日本では闘病者自身が自前で作り出し、共有し、利用してきたのである。ワシントンポスト記事を読んで当方が「今頃なぜ・・・」と首をひねったのは、以上のような日本の闘病ネットワーク文化の先進性に日々接触してきたからである。日本のウェブ闘病記を軸とする闘病ネットワーク圏は、米国の状況などと比べても、はるかに先進的なのだ。この記事中に出てくるいくつかのエピソードを読んでも、その確信は一層強まるばかりであった。
だから、新しい医療ウェブサービスの開発を目指す当方や他のベンチャー企業は、まずこの「闘病ネットワーク圏」を十分に理解し、信頼し、研究し、その先進性をどのように活かすかという方向で事業開発すべきだと思う。われわれの眼前には「闘病ネットワーク圏」という膨大で豊饒な資源があり、それを所与の前提として、この「闘病ネットワーク圏」から「生かされる」かたちで新規事業は構想されるべきだと思う。われわれはTOBYOが、そのように「闘病ネットワーク圏」によって「生かされる」ことを願っている。
三宅 啓 INITIATIVE INC.

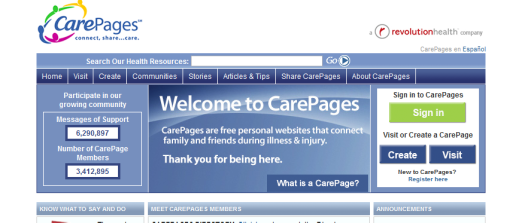

はじめまして。大学院生のYutaと申します。
毎回楽しく・興味深く読ませてもらっています。
こちらに書かれていました「今頃なぜ・・・」という記事は,他の分野についてもよく目にすることがあります。
今頃取り上げるなんて,と。
なんだかがっかりしたり,おいおいと思ってしまうことは多いですが,今はまさに
「だが、ネットユーザーや闘病者は、以上のどの関係者よりも先を進んでいたのである」
ということなのだと思います。
TOBYOはそのような前線で新しいことを生み出す作業をしているのだと私は感じております。
とても興味深い取り組み,今後とも期待しております。
わたしも前線に加われるよう,技を磨いていきたいと思っています。